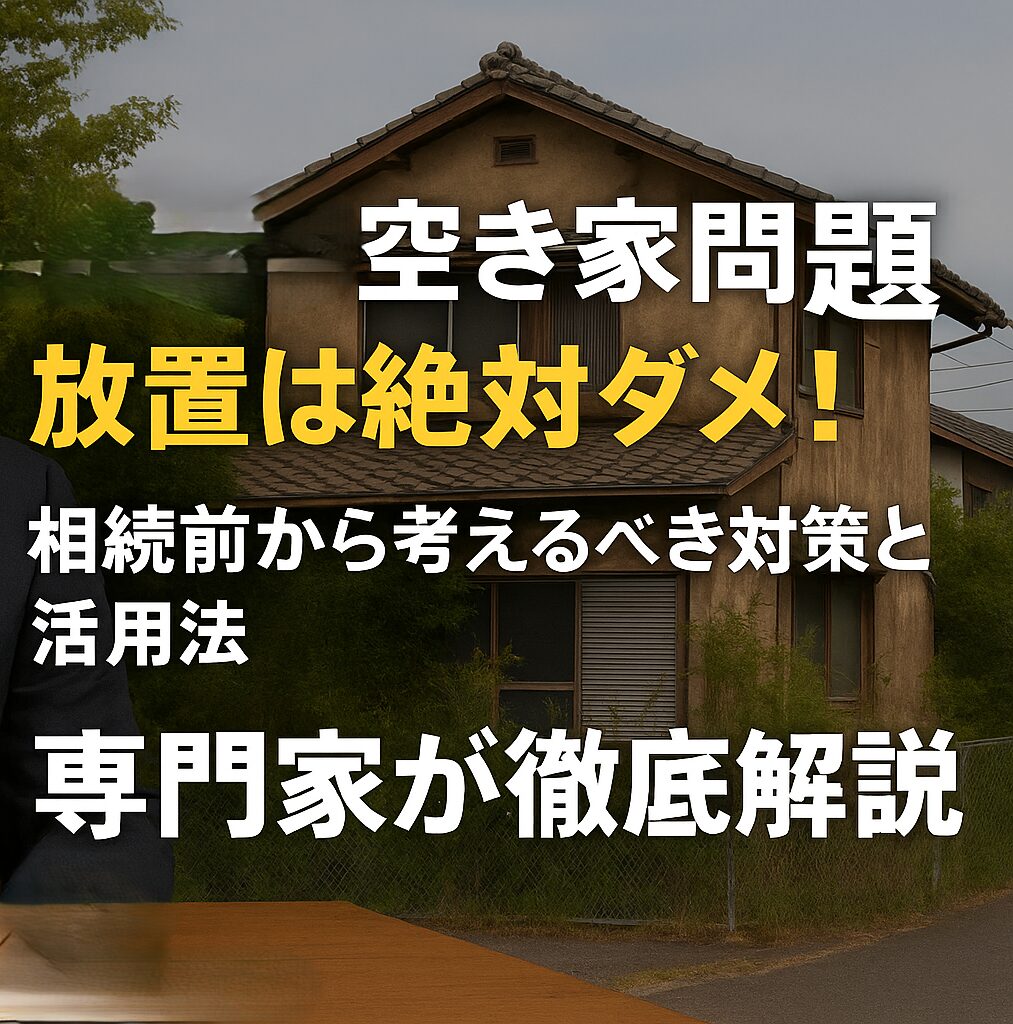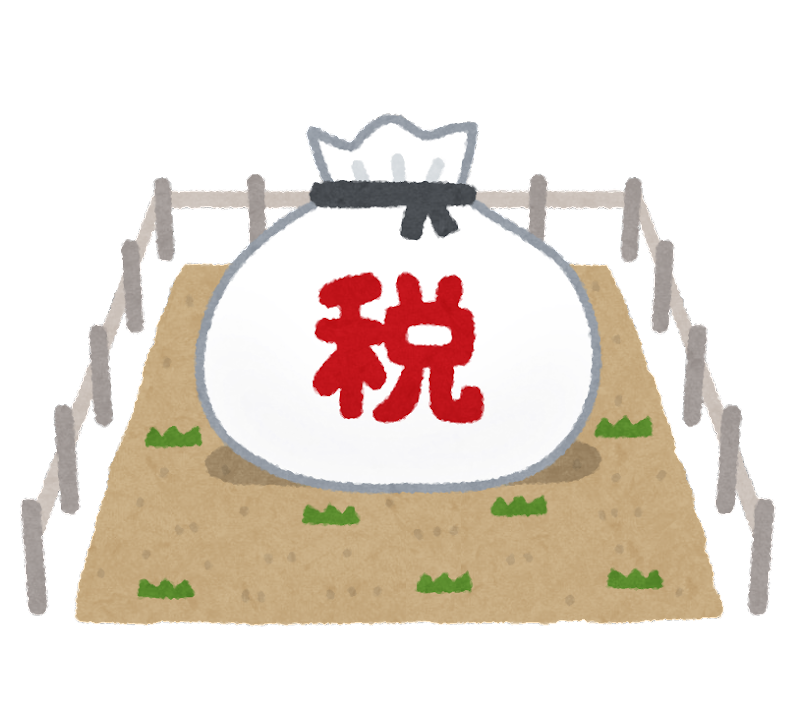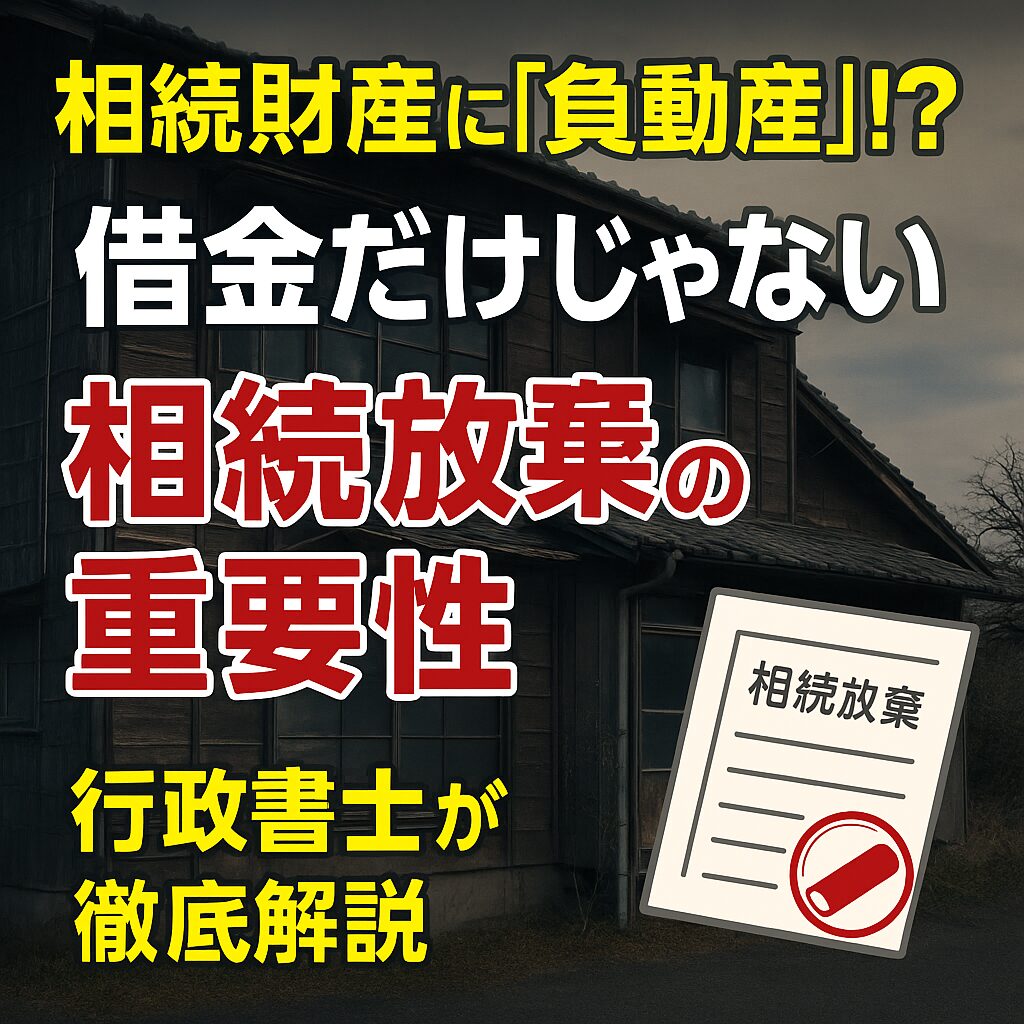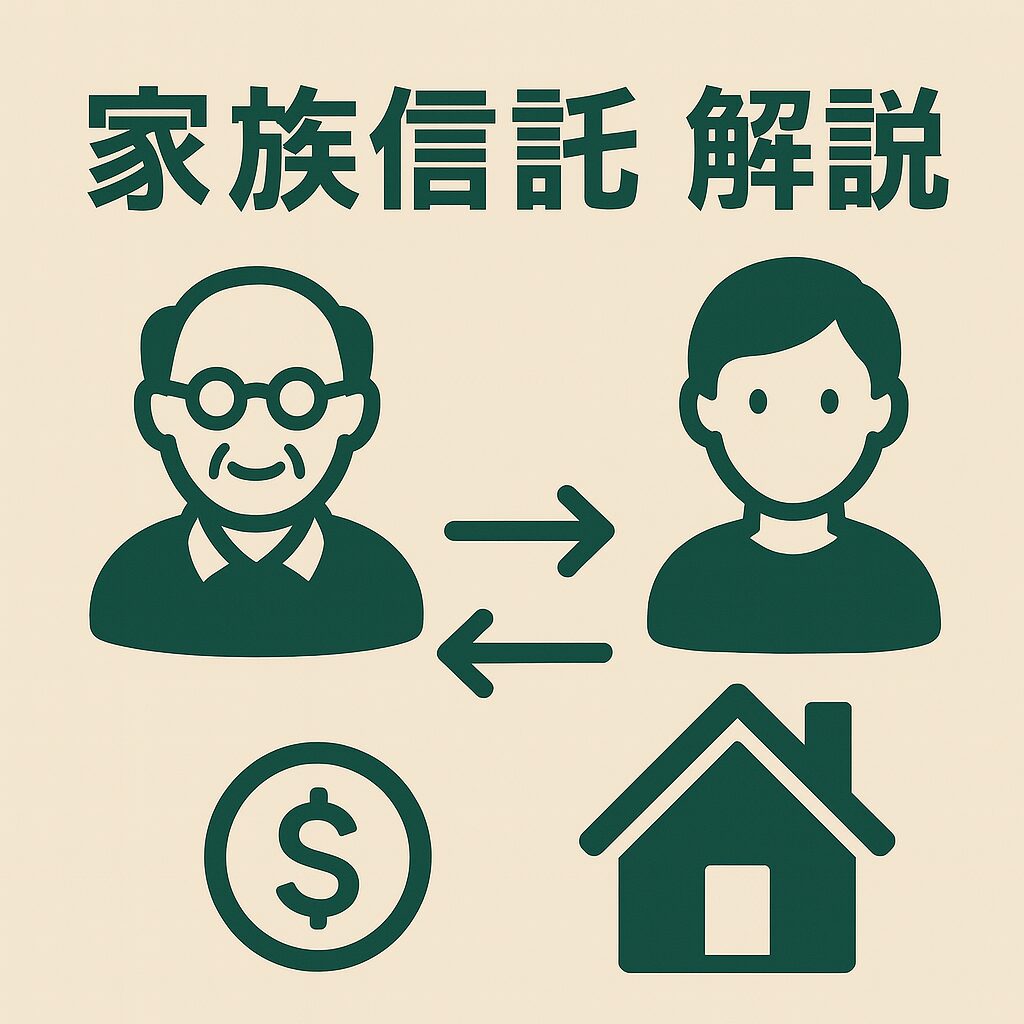行政書士は「街の法律家」として、許認可申請、相続・遺言手続、不動産に関する契約、就労ビザに関する書類作成、マンション管理に関わる法務など、私たちの日常生活に密着した幅広い法務サービスを提供しています。
そんな行政書士に関する法律(行政書士法)が2025年に大きく改正され、特に特定行政書士の職域が拡大されました。今回の改正によって、特定行政書士は従来以上に行政手続における不服申立て(審査請求等)で皆様のお力になれるようになります。
この記事では、この行政書士法改正のポイントと、それによって生じるメリットについて、一般の方にもわかりやすく解説します。
特定行政書士とは何か?
まず特定行政書士とは何かを押さえておきましょう。
特定行政書士は、行政書士のうち日本行政書士会連合会が実施する法定研修を修了し、考査(試験)に合格した者に付与される資格です。平成26年(2014年)の法改正で創設された制度で、特定行政書士には行政に対する不服申立て(行政不服審査)の代理権が与えられています。
つまり、一定の研修と試験を経た行政書士は、行政処分に不満がある依頼者に代わって、その処分の取消しや変更を求める審査請求などの手続きを行うことができるのです。
現在、特定行政書士として登録している行政書士は全国で約6,000人存在します。(当事務所の代表行政書士はその6,000人のうちの一人です!)
特定行政書士になると行政書士証票の色がそれまでの緑から金色に変わり、バッジも一回り大きい特別なものになるなど、見た目にも特別感がありますが、何よりもその責任と役割は非常に重要です。特定行政書士は、役所への書類提出代行や権利義務の書類作成だけでなく、行政不服申立てという行政処分に対する異議申立て手続きまでサポートできるため、依頼者にとってはより頼もしい存在となります。
2025年行政書士法改正のポイント – 審査請求代理権の拡大
2025年6月、行政書士法の改正案が国会で可決・成立し、2026年1月1日から施行されることになりました。この改正ではいくつかの重要ポイントがありますが、中でも注目すべきは特定行政書士が代理できる業務範囲の拡大です。
これまでの課題:活躍の場が限られていた特定行政書士
これまでは、特定行政書士が代理人として行える不服申立て手続きは、「その行政書士自身が作成した書類」に関する許認可処分に対する場合に限られていました。
たとえば、行政書士が依頼を受けて提出した許可申請が不許可になった場合には、その特定行政書士が審査請求を代理できました。しかし、申請書類を本人(依頼者)が自分で作成して提出していた場合や他の行政書士・専門家が作成していた場合には、特定行政書士といえど代理権が認められなかったのです。
それゆえ、「特定行政書士は使えない」と揶揄されることもあったほど、実務上では特定行政書士の活躍の場が限られていました。
改正後の変化:「行政書士が作成できる書類」なら代理可能に
改正後はここが大きく変わります。新しい行政書士法では、特定行政書士が代理できる範囲が「行政書士が作成した書類に係る不服申立て」から「行政書士が作成することができる書類に係る許認可等」に関する不服申立て手続きへと拡大されました。
これには、行政不服審査法にもとづく審査請求、再調査の請求、再審査請求といった手続きが含まれます。
行政不服申立て(審査請求)とは?一般市民にとって何が嬉しいのか
ところで、「審査請求」や「行政不服申立て」という言葉は聞き慣れない方も多いでしょう。
簡単に説明すると、これは行政機関(役所)が下した処分に不服(納得がいかない、間違っていると思う)場合に、その処分の見直しを求める制度です。裁判を起こす前の段階で利用できる行政救済手段で、できるだけ手続きを簡易に、そして迅速に進めて国民の権利利益を救うことを目的としています。
許認可の専門家が不服申立てもサポート
例えば、建設業の許可申請を出したのに不許可になってしまった、飲食店営業の許可が下りなかった、といったケースで「それはおかしいのでは?」と感じた場合、この審査請求という手段で異議を申し立てることができます。審査請求を行うと、原処分を行った役所とは独立した審査機関(例:総務省の行政不服審査会)がその処分の適法性・妥当性を検証し、場合によっては処分が取り消されたり変更されたりします。
今までは、こうした行政への不服申立ては申請者自身で行うか、あるいは弁護士に依頼するケースが主でした。しかし特定行政書士制度の拡充によって、行政書士にもより幅広く頼れるようになる点が市民や企業にとって大きなメリットです。
行政書士は日頃から許認可申請の手続きを数多く代行しており、各種行政手続に精通しています。そのため、不服申立ての場面でも事実関係や法令を踏まえた的確な主張・立証を行いやすい専門家と言えます。今回の改正で、依頼者にとってはより身近な費用感で専門的な再審査手続きを利用できる可能性が高まります。
在留資格(ビザ)申請での新たな可能性
また、在留資格(ビザ)申請の分野も注目ポイントです。現行制度では、入管業務(ビザ申請)の不許可について行政書士が不服申立てを代理することはできませんでした。
しかし、法改正後は「行政書士が作成することができる書類」に係る許認可が対象に含まれるため、将来的にはビザ不許可に対する審査請求も特定行政書士が代理できる可能性が開かれました。出入国在留管理庁での手続きに精通した行政書士が、ビザ申請の段階だけでなく不許可後のフォローまで一貫してサポートできるようになれば、在留資格で悩む外国人の方々や企業にとっても大きな助けとなるでしょう。
その他の改正点:デジタル社会対応と無資格者対策
今回の法改正には、特定行政書士の権限拡大以外にも重要なポイントがあります。
デジタル社会への対応が「職責」に
一つは「行政書士の使命・職責」の明確化です。改正法では、行政書士の職責として以下の点が明記されました。
- 常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行うこと。
- デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用等を通じて、国民の利便の向上及び業務の改善進歩を図るよう努めること。
他の士業(弁護士や司法書士など)でも使命規定はありますが、デジタル社会への対応を職責として規定したのは行政書士法が初めてです。社会や行政のDX化が進む中、行政書士もITの活用によって業務効率を上げ、依頼人の利便性を高める努力が求められます。
無資格者による業務の取り締まり強化
もう一つは「無資格者による業務」の取り締まり強化です。従来より無資格者が報酬を得て書類作成業務を行うことは禁止されていましたが、改正法ではその規制を明確化し、違反者本人だけでなく依頼した法人等も処罰可能な両罰規定を設けました。
これにより、補助金申請代行や許認可書類の作成は、有資格の行政書士に依頼すべきことが改めて明示されたと言えます。
当事務所のサポート内容とご相談について
以上のように、行政書士法の改正によって特定行政書士を中心に行政書士の活動範囲が広がり、皆様の権利利益を守るための頼れる場面が増えてきました。当事務所(東京都多摩 相続・遺言相談所/小平一橋大学前行政書士事務所)でも、特定行政書士として今回の改正を踏まえた対応を整えております。
当事務所では、以下のような幅広い業務に対応しております:
- 建設業の許可等、各種許認可申請の代行・代理
- 相続手続きや遺言書作成のサポート
- 成年後見の申立て支援(司法書士等の紹介など)
- 不動産関連の契約書作成や手続き代理
- マンション管理に関する法務相談
万一不許可となった場合の審査請求手続きまで一貫してお任せいただけます(改正により正式に審査請求代理が可能となりました)。許認可でお困りの際はぜひご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。当事務所では初回のご相談は無料で承っております(対面・オンライン問わず)。行政手続きや相続・遺言などでお悩みの方、許可申請に不安がある方、そして万一申請が不許可となってしまった方も、どうか一人で抱え込まず専門家にご相談ください。
今回の法改正で実現した新たなサポート体制を最大限活用し、皆様の権利と暮らしを守るお手伝いをさせていただきます。
相続手続きでお困りなら、今すぐご相談ください
「何から手をつけていいか分からない」「自分の場合はどうなるの?」とご不安な方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
当事務所では、相続に関するご相談はもちろん、遺言書作成、遺産分割協議書作成、他の士業との連携による手続きまで、相続手続きをワンストップでサポートいたします。
土日祝日も対応可能です。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせいただき、お悩みをお聞かせください。専門家と一緒に、円満な相続を実現しましょう。
対応エリア:東京都全域、埼玉県南部、神奈川県北部(その他地域 応相談)