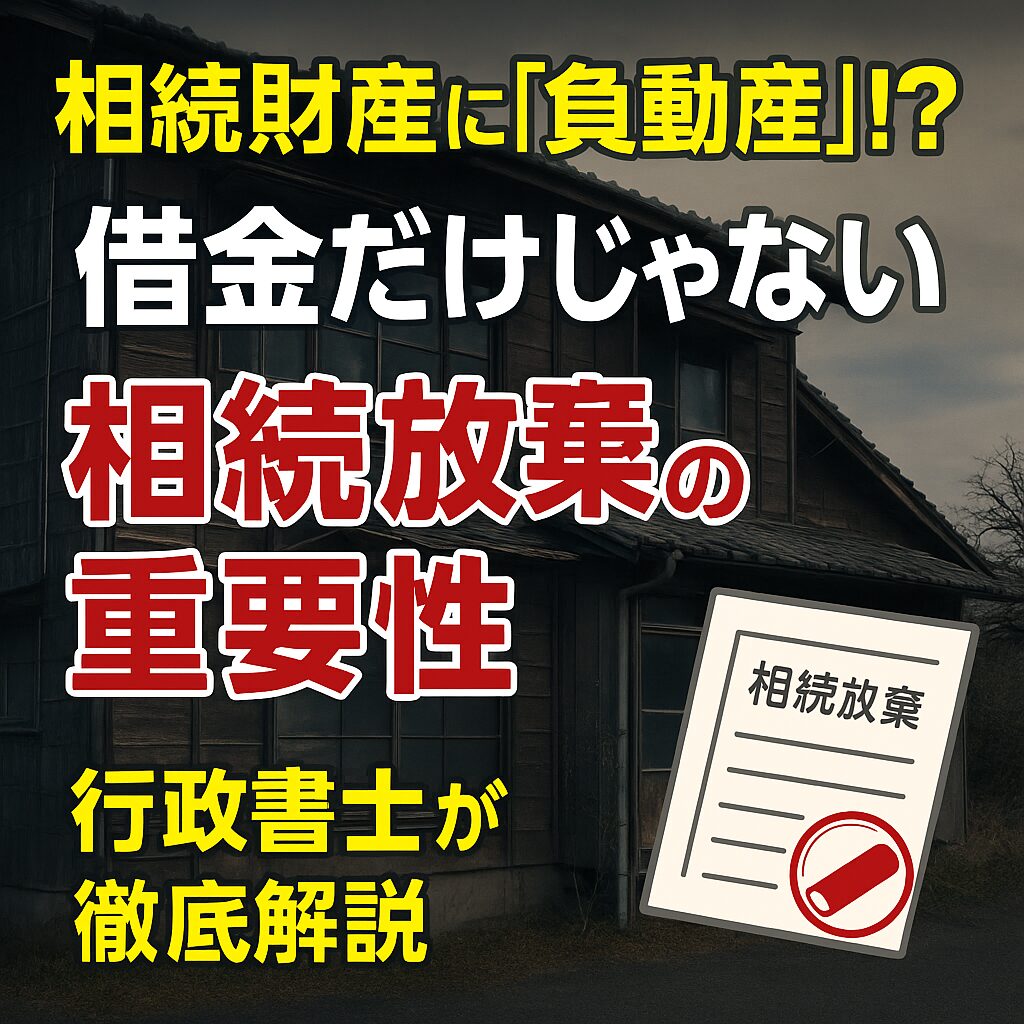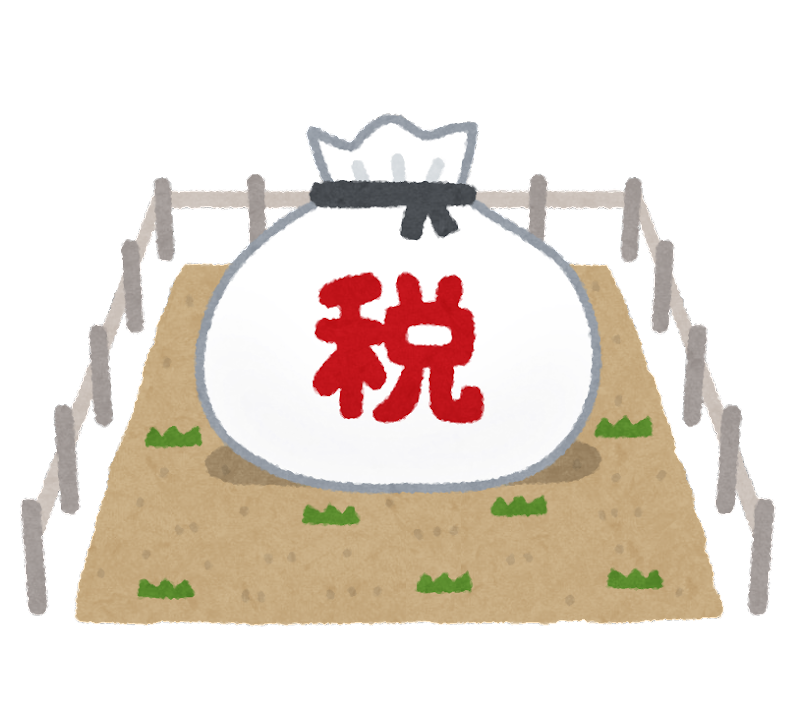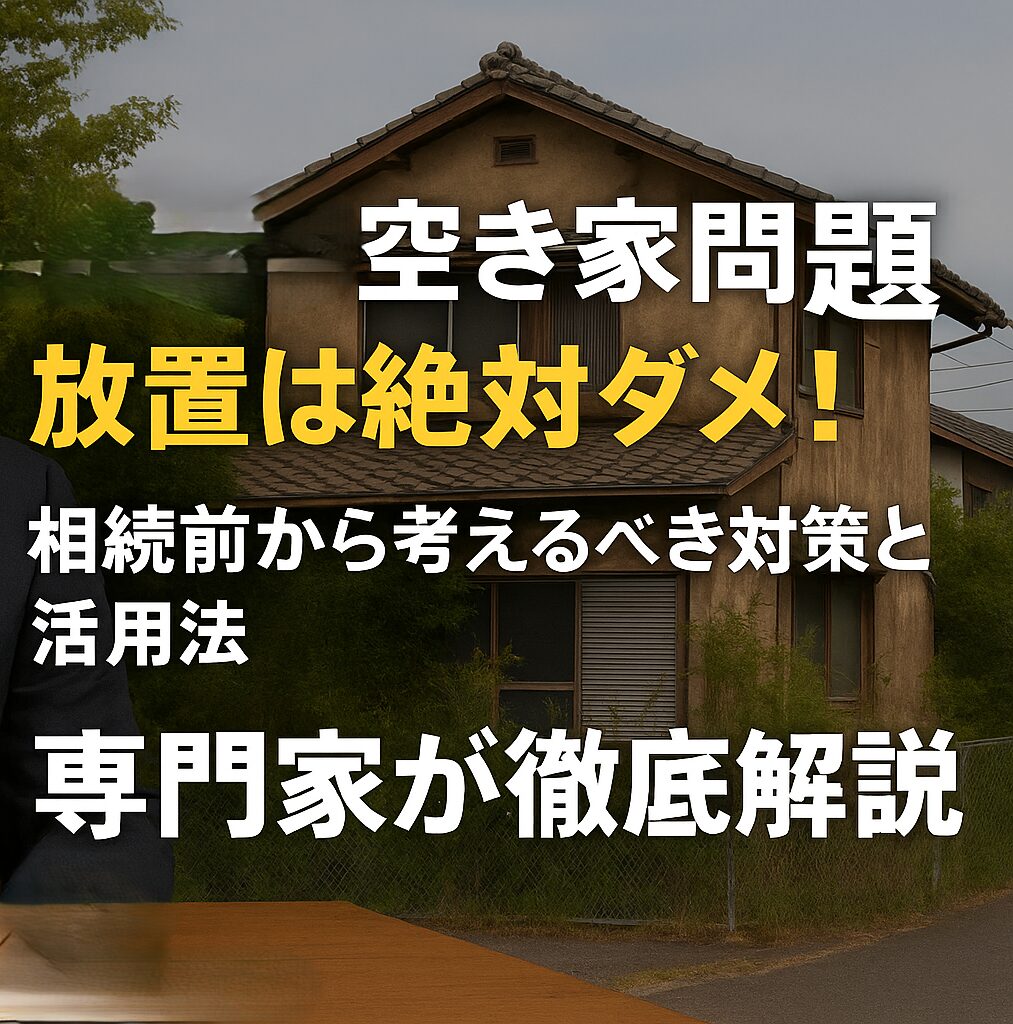2024年4月1日から、不動産の相続登記(名義変更)が義務化されました。
この新しいルールを知らないままでいると、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
この記事では、相続登記義務化のポイントや罰則の内容、期限に間に合わない場合の対処法「相続人申告登記」などを、法律初心者の方にも分かりやすく解説します。
過去の相続にも適用される重要な内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
相続登記の義務化とは?誰が・いつまでに・何をすべきか
「相続登記の義務化」とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に、その不動産の名義を相続人へ変更する手続き(相続登記)を法的に義務付ける新しい制度です。2024年4月1日からスタートしました。まずは、この制度の重要ポイントを3つに分けて確認しましょう。
義務化の3つの重要ポイント
- 対象者:相続や遺贈(遺言による贈与)で不動産を取得した相続人全員
- 対象不動産:土地、建物、マンションなどすべての不動産
- 期限:原則として、相続の開始を知り、かつ不動産の取得を知った日から3年以内
例えば、親が亡くなり、自分が家や土地を相続することになった場合、その事実を知った日から3年以内に、法務局で名義変更の手続きを完了させる必要があります。
注意!この義務化は「過去の相続」にも適用されます
この法律で特に注意が必要なのは、法律の施行日(2024年4月1日)より前に発生した相続にも適用されるという点です。「何年も前に親から相続したけど、手続きが面倒でそのままにしている…」というケースも、もはや例外ではありません。
過去の相続については、以下の期限が設定されています。
- 法律の施行日(2024年4月1日)と自分が相続人であることを知った日の、いずれか遅い日から3年以内
つまり、2024年4月1日より前に発生した相続で、まだ登記が済んでいない不動産をお持ちの方は、猶予期間である2027年3月31日までに相続登記を完了させる必要があります。この期限を過ぎると、同様に罰則の対象となる可能性があるため、早めの対応が不可欠です。
登記を怠った場合の罰則は?10万円以下の「過料」について
正当な理由なく、定められた期限内に相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料(かりょう)という行政上のペナルティが科される可能性があります。これは刑事罰の前科とは異なりますが、金銭的な負担が生じる罰則です。
すぐに罰則(過料)が科されるわけではない
「期限を1日でも過ぎたら、即10万円の請求が来る」というわけではありません。手続きの流れは以下のようになっています。
- 法務局が登記されていない不動産を把握する。
- 法務局から相続人に対し、登記を行うよう催告(さいこく)の通知が送られる。
- 催告を受けても、正当な理由なく登記申請を行わない場合に、裁判所の手続きを経て過料が決定される。
つまり、うっかり期限を過ぎてしまっても、法務局からの通知に速やかに応じれば、いきなり過料を科される可能性は低いと言えます。しかし、催告を無視し続けるなど、悪質なケースでは罰則が適用されるため注意が必要です。
「正当な理由」の例としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 相続人が非常に多く、戸籍謄本などの資料収集に時間がかかる場合
- 遺言の有効性を巡って争いがある場合
- 相続人に重病の方がいる、経済的に困窮しているなど、すぐに手続きができない事情がある場合
こうした事情がある場合は、まず法務局に相談することが重要です。詳しくは、法務省のウェブサイトもご参照ください。
なぜ相続登記が義務化されたのか?背景にある「所有者不明土地問題」
今回の法改正の大きな背景には、社会問題となっている「所有者不明土地」の増加があります。
所有者不明土地とは、相続登記がされないまま世代交代が繰り返され、登記簿上の名義人が亡くなった方のままになっていることで、現在の本当の所有者が誰だか分からなくなってしまった土地のことです。
所有者不明土地が引き起こす問題
- 公共事業(道路建設など)の用地買収が進まない
- 災害復興の妨げになる
- 周辺地域の環境悪化(不法投棄、管理不全など)を招く
国土交通省の調査では、日本の土地の約24%が所有者不明土地の可能性があると推計されており、その面積は九州本島の面積を上回るとも言われています。この問題の主な原因が「相続登記の未了」であることから、国はこれ以上の発生を防ぐために、相続登記を義務化するという大きな決断を下したのです。
【重要】3年以内に登記できない場合の救済策「相続人申告登記」
「相続人が多くて、遺産分割協議が3年以内にまとまりそうにない…」
「誰が不動産を相続するかでもめていて、手続きが進まない…」
こうしたケースは決して珍しくありません。ご安心ください。法律は、このような場合に備えて「相続人申告登記」という新しい制度を用意しています。
相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、遺産分割協議が成立していなくても、「自分が相続人の一人であること」を法務局に申し出るだけで、ひとまず相続登記の申請義務を果たしたとみなされる簡易的な手続きです。
相続人申告登記のメリット
- 過料のリスクを回避できる: 3年の期限内にこの申告さえしておけば、義務違反にはなりません。
- 手続きが簡単: 相続人の一人が単独で申請できます。遺産分割協議書などは不要です。
- 費用が安い: 登録免許税はかかりません(非課税)。※戸籍謄本等の取得費用は別途必要
この申告をしておくことで、遺産分割協議にじっくり時間をかけることができます。ただし、これはあくまで暫定的な措置です。後に遺産分割が成立し、不動産を取得する人が決まったら、その日から3年以内に正式な相続登記(所有権移転登記)を行う必要がありますので、忘れないようにしましょう。
手続きの詳細は、法務省の「相続人申告登記について」のページで確認できます。
相続したくない…そんな時のための2つの制度
中には「利用価値のない土地を相続してしまい、管理費や税金の負担だけが重い」という方もいるでしょう。そうした場合に検討できるのが「相続放棄」と「相続土地国庫帰属制度」です。
① 相続放棄
家庭裁判所で手続きをすることで、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて受け継がないようにする制度です。相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったことになるため、相続登記の義務も発生しません。ただし、原則として相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きが必要であり、特定の不動産だけを放棄することはできない点に注意が必要です。
② 相続土地国庫帰属制度
相続または遺贈によって取得した不要な土地を、国に引き取ってもらう制度です(2023年4月開始)。ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、建物がない更地であること、境界争いがないことなど、厳しい要件が定められています。また、審査に合格しても、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。
「どうしても手放したい土地がある」という場合の最終手段の一つですが、誰でも利用できるわけではない限定的な制度と理解しておきましょう。詳しくは法務省の特設サイトをご覧ください。
相続登記をスムーズに完了させる3つのコツ
相続登記の義務化に対応し、円滑に手続きを終えるために、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
- 遺言書を活用する:
生前に財産を残す方が「誰にどの不動産を相続させるか」を遺言書(特に公正証書遺言)で指定しておけば、相続人間の話し合いが不要になり、手続きが格段にスムーズになります。遺産分割での争いを防ぐ「争続対策」としても最も有効です。 - 専門家に依頼する:
相続登記には、戸籍謄本の収集から遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成まで、専門的で煩雑な手続きが伴います。司法書士や行政書士といった専門家に依頼すれば、時間と手間を大幅に削減でき、法改正にも的確に対応してもらえます。 - 早めに着手する:
何よりも大切なのが、相続が発生したら先延ばしにせず、すぐに動き出すことです。時間が経つと、新たな相続が発生(二次相続)するなどして関係者が増え、手続きがより複雑化するリスクがあります。
【Q&A】相続登記義務化に関するよくある質問
Q1. 相続人が複数いる場合、誰が手続きをするのですか?
A1. 遺産分割協議で不動産を取得することになった相続人が申請義務を負います。また、法定相続分で共有の登記をする場合は、相続人の一人から申請することも可能です。期限内に遺産分割がまとまらない場合は、各相続人が個別に「相続人申告登記」を行うことで義務を果たすことができます。
Q2. 相続登記にかかる費用はどれくらいですか?
A2. 主に、法務局に納める「登録免許税」と、専門家に依頼する場合の「司法書士・行政書士報酬」がかかります。登録免許税は、原則として不動産の固定資産税評価額の0.4%です。報酬は、不動産の数や評価額、相続人の人数などによって変動します。
Q3. 自分で手続きすることは可能ですか?
A3. はい、ご自身で手続きすることも可能です。ただし、多くの書類を正確に収集・作成する必要があり、法務局の窓口は平日の日中しか開いていないため、時間と労力がかかります。書類に不備があれば何度も足を運ぶことになるため、不安な方や時間がない方は専門家への依頼をおすすめします。
まとめ:義務化は他人事ではない!早めの相談と準備で安心な相続を
2024年4月から始まった相続登記の義務化は、不動産をお持ちのすべての方にとって無視できないルール変更です。「知らなかった」では済まされず、放置すれば過料という罰則のリスクがあります。
しかし、制度を正しく理解し、計画的に準備すれば、何も恐れることはありません。期限内に手続きが難しい場合でも「相続人申告登記」という救済策が用意されています。
何よりも重要なのは、問題を先送りにせず、早めに行動を起こすことです。相続登記を完了させることは、法的な義務を果たすだけでなく、大切な財産を巡る将来のトラブルを防ぎ、安心して次の世代へ引き継ぐための重要なステップです。
相続手続きでお困りなら、今すぐご相談ください
「何から手をつけていいか分からない」「自分の場合はどうなるの?」とご不安な方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
当事務所では、相続登記の義務化に関するご相談はもちろん、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、提携司法書士との連携による登記申請まで、相続手続きをワンストップでサポートいたします。
土日祝日も対応可能です。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせいただき、お悩みをお聞かせください。専門家と一緒に、円満な相続を実現しましょう。
対応エリア:東京都全域、埼玉県南部、神奈川県北部(その他地域 応相談)