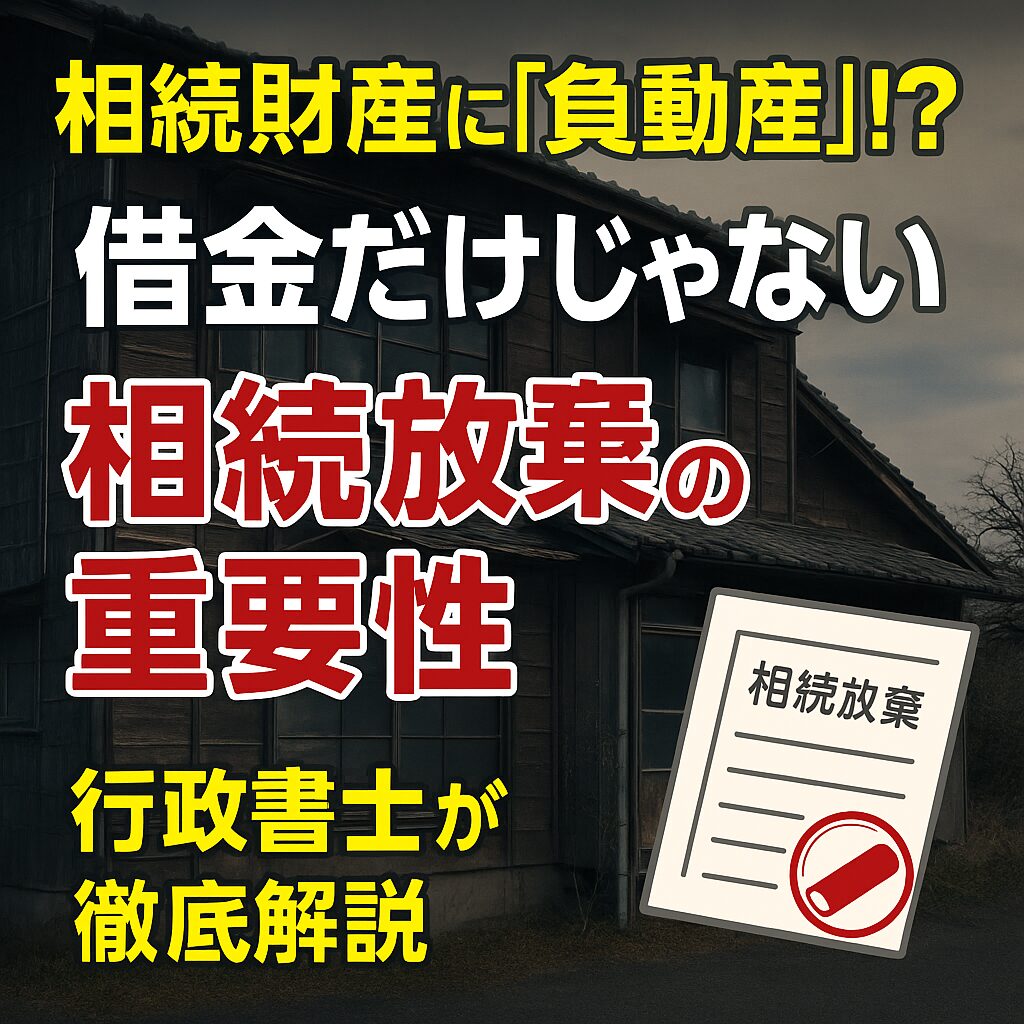
「相続」と聞くと、預貯金や価値のある不動産といったプラスの財産を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、実際には利用価値が低い山林や原野、買い手のつかない古い家、管理費ばかりがかさむリゾートマンションなど、所有しているだけで負担になる「負動産」を引き継いでしまうケースも少なくありません。
「借金はないから相続放棄は関係ない」と思っていませんか?
実は、このような「負動産」も相続放棄を検討すべき重要な理由の一つになり得るのです。
この記事では、相続財産に「負動産」が含まれていた場合にどう対処すべきか、相続放棄という選択肢を中心に、行政書士が法的なポイントを分かりやすく解説します。
「負動産」とは? 相続で頭を悩ませる困った財産
「負動産」という言葉は法律用語ではありませんが、一般的に以下のような不動産を指すことが多いです。
利用価値の著しく低い土地
- 売却も活用も難しい山林、原野、傾斜地
- 接道義務を満たしていない、あるいは再建築が不可能な土地
- 農地法などの規制により活用が制限される農地(後継者がいない場合など)
価値の低い、または管理困難な建物
- 老朽化が激しく、多額の修繕費や解体費用が見込まれる空き家
- 旧耐震基準のマンションや、管理状態の悪いマンションの一室
- 買い手がつかない地方の戸建てや別荘
- 管理費や修繕積立金の負担が重いリゾートマンションの会員権や区分所有権
権利関係が複雑な不動産
- 多数の共有者がいて、意思統一や処分が困難な共有名義の不動産
- 境界が未確定で、隣地とトラブルを抱えている土地
これらの「負動産」は、所有しているだけで固定資産税や管理費といった経済的負担が継続的に発生し、さらに管理を怠れば損害賠償責任を問われるリスクも伴います。
なぜ「負動産」のために相続放棄を検討するのか?
相続財産に借金などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討するのは自然な流れです。しかし、借金はなくても、「負動産」の存在が相続放棄を考える大きな理由となることがあります。
永続的な経済的負担からの解放
- 固定資産税・都市計画税は、不動産を所有している限り毎年課税されます。利用価値のない「負動産」のために、永続的に税金を支払い続けるのは大きな負担です。
- マンションであれば管理費・修繕積立金、土地であれば草刈りなどの管理費用も発生します。
管理責任・法的リスクの回避
- 空き家を放置して倒壊したり、管理不備で第三者に損害を与えたりした場合、所有者は損害賠償責任を負う可能性があります。特に「特定空き家」に指定されると、行政からの指導や命令、最終的には行政代執行による解体費用を請求されることもあります。
- 相続放棄をすれば、これらの管理責任や法的リスクから解放されます。
精神的負担の軽減
「どうしようもない不動産を抱えてしまった」という精神的なストレスは想像以上に大きいものです。相続放棄によって、この重荷から解放されることは大きなメリットと言えるでしょう。
次世代への負の連鎖の回避
自分が「負動産」を相続してしまうと、将来的に自分の子供たちが同じ問題で悩む可能性があります。相続放棄をすることで、この負の連鎖を断ち切ることができます。
相続放棄の手続きと注意点:知っておくべき基本
相続放棄は、家庭裁判所に申し立てを行うことで、初めから相続人でなかったものとみなされる法的な手続きです。
手続きの期限
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。
必要書類
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- その他、相続関係に応じて追加書類が必要になる場合があります(例:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など)。
相続放棄の効果
相続放棄が受理されると、その相続人はプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しません。一度相続放棄をすると、原則として撤回することはできません。
相続財産の処分行為に注意
熟慮期間中であっても、相続財産の一部を処分したり、隠匿したりすると、単純承認(すべての財産を相続すること)したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。例えば、被相続人の預貯金を引き出して自分のために使ったり、不動産を売却したりする行為は注意が必要です。
相続放棄を検討すべき「負動産」の具体例
どのような「負動産」の場合に相続放棄を真剣に検討すべきでしょうか。
明らかに処分・活用が困難で、維持費だけがかさむケース
- 交通の便が悪く、買い手も借り手も見込めない山奥の土地や原野。
- 老朽化が著しく、解体費用が売却価格を大幅に上回るような空き家。
管理責任が過大で、将来的なリスクが高いケース
- 崖地に建っているなど、自然災害による倒壊リスクが高い物件。
- アスベスト除去費用が高額になることが判明している建物。
共有名義で、自分の意思だけではどうにもならないケース
- 他の共有者と連絡が取れない、または協力が得られず、売却も管理もできない共有不動産の一部持分。
限定承認では対応が難しい、または手間がかかりすぎるケース
- 財産調査に時間がかかりすぎ、限定承認の手続き期限に間に合いそうにない場合。
相続放棄以外の選択肢はあるか?
「負動産」があるからといって、必ずしも相続放棄が唯一の道ではありません。状況によっては、以下のような選択肢も検討できます。
限定承認
被相続人の借金などのマイナスの財産が、プラスの財産の範囲内でどれだけあるか不明な場合に有効な手続きです。相続したプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を弁済すればよく、もし財産が残ればそれを相続できます。
ただし、手続きが非常に複雑で、相続人全員で共同して行わなければならない(相続放棄した者を除く)などの制約があり、申述費用(収入印紙、郵便切手)のほか、官報公告費用なども別途かかり、時間も要するため、利用されるケースは相続放棄に比べて少ないのが現状です。
相続財産清算人の選任申立て(旧:相続財産管理人)
相続人全員が相続放棄をした場合や、相続人がいない場合、利害関係人(債権者など)や検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産清算人(2023年3月までは「相続財産管理人」と呼ばれていました)を選任することがあります。相続財産清算人は、相続財産を管理・清算し、最終的に国庫に帰属させる手続きを行います。
ただし、相続財産清算人の選任には予納金(数十万~百万円程度)が必要となることが一般的です。
相続土地国庫帰属制度の利用
2023年4月27日から施行された制度で、相続または遺贈により取得した土地で、一定の要件を満たすものについて、法務大臣の承認を受けて国庫に帰属させることができる制度です。
ただし、建物がある土地は対象外(解体が必要)、土壌汚染がないこと、境界が明らかであることなど、多くの要件があり、審査には時間もかかります。また、審査手数料(土地一筆あたり14,000円)に加え、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。すべての「負動産」がこの制度を利用できるわけではありません。
現状のまま売却・寄付を試みる
不動産業者に相談し、現状のままでも引き取ってくれる買い手を探したり、あるいは地方自治体や法人などに寄付を打診したりする方法です。非常に安価での売却や、寄付を受け付けてもらえないケースも多いですが、試してみる価値はあります。
「負動産」の相続でお困りなら、行政書士にご相談ください
「負動産」を相続してしまった、あるいはその可能性がある場合、ご自身だけで判断するのは非常に困難です。法的な手続きの期限もありますし、誤った対応をしてしまうと取り返しのつかないことになる可能性もあります。
私たち行政書士は、以下のようなサポートを通じて、皆様の「負動産」に関するお悩み解決をお手伝いできます。
相続関係調査・財産調査のサポート
誰が相続人で、どのような財産があるのかを正確に把握するための調査をお手伝いします。
相続放棄に関するご相談・手続き支援
相続放棄の意思決定に関するご相談や、申述に必要な戸籍謄本等の収集の代行、相続放棄申述書の記載内容に関する一般的なアドバイスなどを通じて、スムーズな手続きを支援します。
※注:家庭裁判所に提出する相続放棄申述書そのものの作成代行や提出代理は、司法書士または弁護士の業務となります。行政書士はこれらの専門家と連携し、お客様をサポートします。
限定承認手続きの相談
限定承認が適切なケースかどうかのアドバイスや、必要な手続き(他の専門家との連携を含む)についてご案内します。
相続土地国庫帰属制度利用の相談・申請サポート
制度利用の可否判断の助言、申請に必要な書類の作成、法務局への申請代理、添付書類の収集代行など、制度利用に向けた一連の手続きをサポートします。
※注:承認後の土地の権利変動に関する登記手続きが必要な場合は、司法書士との連携が必要になります。
遺産分割協議書作成サポート
相続人間で「負動産」の取り扱いについて話し合い、合意に至った内容を法的に有効な書面(遺産分割協議書)として作成します。
(ただし、紛争性のある事案については弁護士の領域となります)
各種専門家との連携
必要に応じて、弁護士(紛争案件の場合)、司法書士(不動産登記、裁判所提出書類作成)、税理士(相続税申告)、土地家屋調査士(境界確定)、不動産鑑定士(財産評価)といった他の専門家と緊密に連携し、ワンストップで最適な解決策をご提案します。
(行政書士は、これらの専門家の独占業務を直接行うことはできませんが、適切な専門家への橋渡しや、連携による手続き全体の円滑化を図ります。)
相続財産に「負動産」が含まれているかもしれないと不安に感じたら、まずは熟慮期間である3ヶ月を意識し、できるだけ早く専門家にご相談ください。当事務所では、お客様の状況を丁寧にお伺いし、最善の道筋を見つけるお手伝いをさせていただきます。手遅れになる前に、勇気を出して一歩踏み出しましょう。






